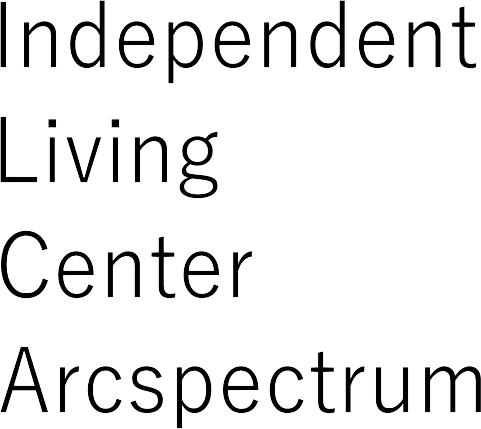ひゅうまん京都 寄稿文2015年5月
私たちの介助心得の一つめは「障害者の主体性を尊重してください」であり、介助者をつけて暮らす障害者たちには「介助者の自主性を尊重してください」となる。
いわずもがな、主体性とは、何をやるかは決まっていない状況で自分で判断し行動することであり、どんな介護資格を取得するときでさえ支援の基本となる「自己選択・自己決定」と同義であって、それを尊重したり推し量るのがニーズアセスメントの基本である。つまりもともと、障害者の主体性を尊重してくださいというとき何でもかんでも障害者のいうことが尊重されるべきである、のとは違う。とすると、逆もまた然りで、「障害者はわがままだ」「好き勝手言っている別世界 の住人」、なんてことをいってゴチて腐ってもいけない。
その理由を言おう。それは、主体性を尊重するということは、他者の自主性があって初めて成り立つものだからである。自主性とは、やるべきことは明確でその行動を人に言われないで率先して自らやること、である。つまりこれは団体・事業所の理念、介助者としての行動基準、どっかの国の個人介助者でもない限り日本の介護者はどこかの事業所に所属しているわけで、組織人を自覚しているものならば、その団体・事業所の理念や行動基準にもとづいて介護をするということである。それがうまくなっていない。主体性が誰にあり、自主性は誰と誰が持つのかが、ごっちゃになっているのが日本の福祉である。
具体的に言おう。主体性が尊重されるには、自己選択・自己決定の尊重と自己選択・自己決定のための選択肢の提供がなければいけない。これが本当の意味でのサポートである。とりわけ、健常者社会のなかで育った障害者はあれをしてくれこれをしてくれというのが明確だ。それはそうしないと生きていけないと言われてきたためだ。だからその障害者にとっては自己の尊厳の大切な部分であり、ケチをつけられることを極端に嫌う。一方で、幼少期から親元施設などで?愛もしくは放任で育ってきた障害者は、自己選択・自己決定をひどく難しがる。そして二重三重にも本音を隠す。人の顔色を見ないと生きられなかったからだ。ちょっとその暮らしを想像すればわかる。そしてそもそも社会性をひどく欠如させられて(本人がそう望んだのではなく!)生きてきたので、社会性が未熟である。
だから、である。いま目の前にある介護現場を思い返すことができる。自己選択・自己決定が明確な場合、自主性の余地がないように思える。一方、自己選択・自己決定をしうる主体性が未熟な場合、圧倒的な自主性で関わり一定の域をこえるとそれは介護者の主体性ではないかと見まごう状況となる。長年の経験で、自主性が尊重されたり許されない現場の介護者は必ず腐る。未熟な主体性と介護者の主体性が現場に混在するときは、また必ず介護者が腐る。いま求人をするとき、介護とか、介助という言葉はNGワードで人が来ない。そういったイメージは離職が高い職業の一つとしてつきまわっている。
そもそもこういった問題が介護現場にあるが、これは介護問題でもなんでもない。そもそも社会教育の問題であって、介護現場で頭をかかえる人たち(私のような)は社会から担わされたニーズ(しかも過大だ!)を担っているにすぎないことを自覚する必要がある。
介護もサービス業の一つである。といえば、分かりが良いのと同時になんか薄ら寒いイメージもともなうが、飲食店に入れば注文は聞かれるし(=どんな支援が必要か?をまず聞くこと)、店は注文をとったら厨房にオーダかけて調理をし提供するし(=求められている支援をきっちりおこなうこと)、客が店をでた隙にそのどんぶり鉢をみて不味かったか美味かったかを確かめる訳だし(=その人にとって良い支援だったかを確認すること)、旨さとサービスの質が良ければそれはそのまま売上に直結する(=支援した人の気持ちを受けとめて良いサービスに生かすこと)。ただただ、シンプルにそんな仕事であると分からなければいけない。まあ、ブラック会社がもてはやされ焦げたのれんの気味悪さに敬遠される質のよい店があるのはどこも一緒で、それは需要と供給の足元をみられた結果だ。この国のブラックな連中に。
私と私のもとで介護をする若い人、すべての人にそんな話をする。結局このことでずっと長い間混乱し、混同し、馴れ合い、助け合い、それらがそうであってもうまくいくときもあればうまくいかない時もあるが根本的な事柄である。全部がうまくいかない訳ではないからほんのちょっと工夫すれば解決することは山ほどある。