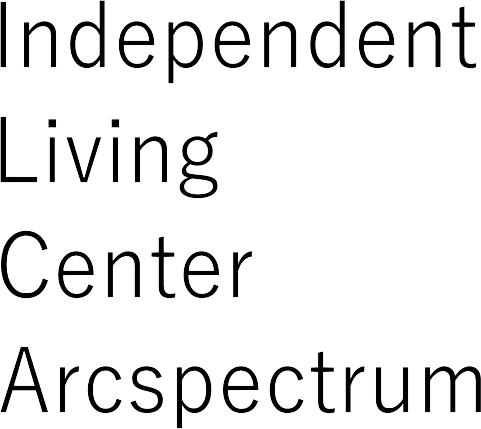ひゅうまん京都 寄稿文2015年5月
わたしたちの介助心得の二つめは「障害者のペースを守ってください」であり、障害者にとってみればそれは「指示によってみずからの生活を作ってください」ということになる。
前回お話ししたように、介護における主体性を尊重するとは、本人の「自己選択・決定を尊重する」もしくは「自己選択・決定をするための選択肢の提供」を必要とし、これは介護におけるサポート(=自主性)という言葉に置き換えができる。とすれば、主体性のかなめは指示であり、自主性のかなめは選択肢を提供する豊かな社会経験と多様性を尊重できるかどうか、であろう。
うまく指示が聞けない人は工夫をすればうまく聞けるようになる。まず指示介助を読み解いてみたら良い。指示とは要求と気持ちがセットになったものであり、要求だけで動いている人は気持ち(背景)を聞く努力を、気持ちだけで動いている人は真なる要求を聞く努力をするだけで、より質の増したコミュニケーションとサービスに転化できるし関係性もぐっと良くなる。しかし、これが非常に難しい。本当に難しいのだがこのことが行えれば介護者の資質には磨きがかかる。人としてもそうである。
実際的に考えてみよう。まず要求だけで動いてしまう場合「これして欲しい」「あれして欲しい」と明確であれば介護はそんなに難しくない。大抵、人なりの日常生活行為をしていれば察することができ、その手順もあまり変わることがないためである。しかし、だからこそ先走ってついつい自主性(個人的な!)を発揮しすぎてあれもこれもやってしまう介護者がいる一方、指示されなければ行動を起こせない人もいる。また指示を連発する障害者もいて行為をどのような流れで、どれぐらいの速さで、どの程度行うのかさっぱり分からないことも多いから、じわじわとボディブローが効いてきて誰がか痛みを抱える状態になることが多いのは致し方ない。これはものすごくこう着状態が続いて常態化していって結局うまくいっていると見做されることが多いのであるが、でもどれもうまくいっていない。
そこに必要なのは要求だけで済ませないということだ。介護者は障害者が要求だけをするとき、なぜそれを要求するのか気持ちを言ってもらうように聞いてみること。障害者は要求だけで済ませようとせずどういった気持ちで要求するのかを伝える努力をすること。その双方の自覚が現場にはなければならない。翻って考えてみれば、この社会は要求することには慣れている(ゴネる風潮もある)。要求され答えることに慣れてしまってもいる(依存傾向のある癖はほとんどこれ)。それらに埋もれてしまって、障害者は要求すらしたことがなかったり自分の気持ちをいった記憶がなかったり、あるいは聞いてもらった記憶がなかったりする。それぞれの社会性がみごとに噛み合って介護の在りようが成立してしまうから、脈々と続く既成事実は恐ろしい。
福祉労働分野を見渡せば、よく揶揄されることがあるように好き者がやる仕事として続いてきたことは確かにある。そういうことが好きだからやる訳で、気持ちがあるのは間違いがない。だが、気持ちは環境の産物だから柔軟に対応できる訳ではない。長年培われ育まれたものはすぐには拭えない。しかも他者性のなかで物事を感じる必要があるので想定外の気持ちの変化にはついていかれない。しかも、障害者は上記のことが理由で二重三重にも本音を隠して人間関係を築く癖が(顔色を見て生きる術が身に)あるので、表面的な事実でしか受け取れないことの方が多い。
そこに必要なのは気持ちを行動基準に沿わすことができるかどうかである。その気持ちが団体・事業所の理念、介護者に求められる行動基準にはまらないのであればどちらかの器が小さいので器を変えるべきだとは思う。つまり逆のことを言えば、障害者は介護を使ううえでのルールをきっちり守って自らのニーズを充足するために介護者を連れて行動すること。日常生活行為で介護者が必要ならば、日常生活行為についてその手順・その方法をよく学び指示をもって伝えるということをしたいと思う。
もし気持ちだけで要求がないのであるならば、社会性が成熟するための学習機会を保障する必要性も出てくる。ただし、それは一人の介護者が行ってはいけない。団体・事業所が人の社会性というものの総意をもってその機会を保障すべきだろう。
だから、介護時間のなかで要求・気持ちだけで終わらせる関係性をたがいに築いてはいけない。要求だけする障害者を見て、もう要求されることに辟易している介護者は辟易している暇はない。まだ仕事は終わっていない。気持ちだけでなんとなく続いてきた関係のみを切り取っていては、生活の質は向上しない。そういう時間を十分にかけるいとまさえない介護内容であったり現場であるとしたら、かけられていない時間こそが本当の介護の時間だ。その時間分ぐらいは制度保障すべきだ。もっとも、福祉事業を経営するものは社会から担わされたニーズ(前号参照)には答えることができないことが多い。それは良くも悪くも制度内事業をおこなっているためで、だったとしたら、多様な社会資源のなかから特質したサービスをいかに障害者本人へと繋ぎ合わせるかその調整役にならなければいけない。