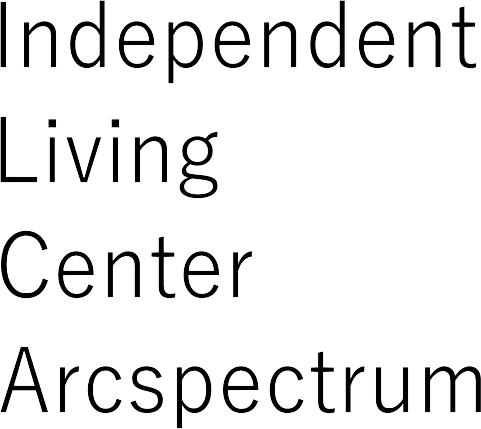ひゅうまん京都 寄稿文2015年8月
世間では戦争法案の是非について議論が起こっています。是非を問う人々の胸中(=動機)もさまざまで、国会前や街中での戦争法案の是非を問う運動パレードは、さながら参加した一人ひとりの日常の戦争を切り取ったものではないか、と考えてしまいます。排外主義的人種差別・宗教差別・高齢障害に対する差別その他、人間社会の抑圧構造すべてが一人ひとりには終わらない戦争ですから、過激な言葉のように聞こえますが、人間社会が作り出した抑圧構造の仕組みと戦うということはある種の戦争なんではないかと考えてしまいます。
ここ数ヶ月、介助者不足の影響もあって、公私ともに妻が介助をしてくれる場面が増えました。妻は同じ職場内のサービス提供責任者ですから、私の介助をしてもなんらおかしくはないのかもしれませんが、さりとて公私ともに介助をしてもらうためにはやはり踏まえておきたいことがあります。どちらかというと、私は一人で生活しているときには日常生活行為すべてに介助を必要としていましたから介助があるのは前提ですが、しかしこれが二人での生活になると妻の気持ちをしっかりと掴みとることが必要になってきて、それが案外容易ではないんです。
私たちの介助心得の三つ目は「障害者の話のペースに合わせる」ということもあり、これは例えば、生活経験豊富な介助者が、一人暮らしをして間もない障害者に対してありとあらゆる介入をした場合、本人にメンタルブロックが起こって伝えたいことが伝えられなくなる現象がよく生じます。特に言語障害をお持ちの人と会話をする場合はゆっくりと丁寧に話を聞いて全体像の把握に努める必要があり、口達者な人は先走りがちですから会話の全体像を聞くことなく介助を進めてしまうことが多いのは否めません。いかんせん私の場合も口達者ですので、よく陥りがちなのが「言葉でなんとかできる」と思いがちなところです。この「言葉でなんとかできる」のと「言葉ではない気持ちが動く」のとその狭間で妻に介助をしてもらうことの容易難さを覚えるという話なのです。
介助者の自主性というものをふとした拍子で認めたとき見えてくるものがありました。彼ら彼女らは、障害者の目の届かないところで周囲の状況を見極めて働くようになります(車いすの前後左右後ろ、横切る自転車など)。大概これまでの私なら、私自身も注意を払っていて見えているわけだからその情報を伝える意味がないなどと言い返したのですが、これらが良くなかったなあ。その自主性をポキっと折ってしまいかねないメンタルブロックが起きてしまいます。もしかしたら「言われんでも分かってる」「保護される対象じゃないねん」「俺の言うことをちゃんと聞いとけ」と自分のことで精一杯だったのかもしれません。
妻の場合、私が「その情報を伝える意味がない」と言っても「いやあんたはみえてない」「くちばっかりや」「無茶な操作して周囲の人怪我させたら大変や」などメンタルブロック返しで百倍くらいにはなります。妻いわく、私が口達者にさせたそうでして、これが対等感の均衡を取り持っているみたいです。
ただ、言いあいはけっして良い会話だとは思えないのですが、もっともそうまでして進言して伝えようとしていることは何なのか?と考えたときに、言葉より「大切な人を守りたい」という気持ちに傾いた言動行動というものはあるんじゃないか、と思います。まあ、あんまり愛されたりそばに愛すべき人がいてくれなかったりで、幼少期愛情欠乏で育ちがちな障害者がその気持ちを受け取ることが一番容易ではないのですが、大切にされているんだという実感から大切にされている「わたし」を自分自身が大切にしなくちゃいけないと思えるようになっていければ、冒頭で書いた、人間社会が作り出した抑圧構造における戦争はそろそろ武器を置いてもいいんじゃないでしょうか。愛すべき人たちと連帯して大切な日々を送ることが、抑圧が一番苦手とするものなんですから。