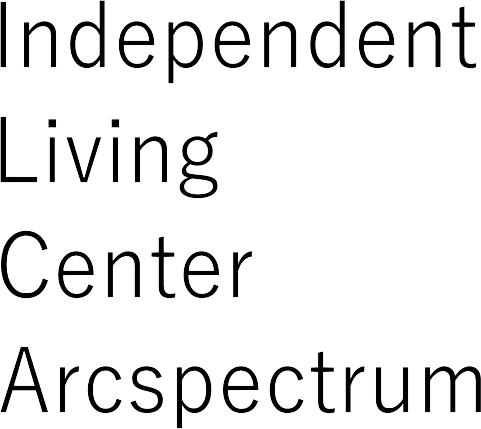ひゅうまん京都 寄稿文2015年9月
私たちの介助心得の四つ目は「障害者の力を奪う行為に敏感になってください」である。非常に重要なことであり、特筆すべきサービス提供の仕方をともなってもいるので、ぜひともみなさんにお伝えしておきたい。この心得は、介助を使う障害者心得にあっては「介助者も一人の人間であり大切な存在であることを忘れないで下さい」となる。それはこれから話すことが理由で他者の人権・尊厳・多様な性質たちを無意識のうちに踏みにじることがあり得るためである。
まず「障害者の力」というものを考えてみたい。誤解を恐れず言うと、私自身は「障害者の」とした段階でそもそも区別・差別の対象として言い表されていると感じて「そんなものはあるんかな?」と思ってしまうけれど、その当事者として、つまり区別や差別をされた経験を生きてきた者を指す言葉としてならば、この障害者は言い得て妙であろう。この区別・差別の歴史は脈々と続いていて、明らかに故意による区別と差別を除いてはほとんどの場合が無知無関心の類となり、そうなれば区別や差別は誰が悪いとか悪くないとか関係はない。
「障害は醜いもの」「障害を持って生きるのは不幸」「障害者は迷惑な存在」「障害者は健常者よりも劣る」と強烈な文言も、時代が変われば「障害は個性」「社会的弱者」「保護すべき/されるべき対象」となり、レジの前に立ち精算するために財布からお金を出しているのは障害者なのに、コンビニの店員がお釣りを返すのは介助者、ありがとうございますと声をかけるのも介助者となってしまう。
コンビニの店員の行為によって障害者の力が奪われるようなことはない。そういった不在にされることが多すぎてもうすでに奪われてしまっているという面もあるが、そのやりとりがそばにいる介助者との間で完結してしまうことで生じる問題こそ障害者の力を奪う最もたる行為となる。たえず本人がいるのに不在にするような行為があり、多くの場合は誰でもそうであるが幼少期に心の傷として影を落としている。幼少期の心の傷は大人になってたえず疼いているわけではなく、よく似た場面よく似た状況下に振りもどされたとき過剰に反応する。どんなに日常生活を力強く生きていようと、介助者との関係を良好に保とうと努力をしていても、根本的に心の傷が癒えていないと、つまりそれを塗り替えるような経験や体験がないと、目の前の完結をさせてしまった介助者を見る目というのはあのとき「私」を不在にさせたあの人と同じに映っている。それは今を生きるという力、今という現実をぶち壊す容易な凶器である。傷は傷を引き起こす。
介助サービスのあり方としては、仮にコンビニの店員が介助者である「私」に向かって本人に関わることを話してきたとしたら「無視」するか「(私は介助者なので)この方に話してくださいが適切な行為となる。ただ「無視」は介助者である「私」自身が居たたまれないこともあり、ましてや本人が社会関係を結ぶうえでは「私」は第三者から見れば他者でもあり、本人と第三者との良好な関係性を結ぶ点となる行為を考えれば「(私は介助者なので)この方に話してください」が良いと思う。これが介助者の自主性である。外(ここでは店員・社会)に向かっては脈々と続いてきた誤った歴史を止める力であり、内(ここでは障害者の)に向かっては傷をえぐるようなことを避け新しい当事者主体・主体性を尊重する歴史を切り開く力とはなっていく。
介助を使い生活する障害者は程度の差はあれ、個人的な心持ちの差はあれど自分が不在にされていることは知っている。そんなつもりで行っていないという人がいるのも知っている。相手が気づく気づかないの狭間で懸命に過去に立ち戻らず今を生きよう、今という現実を大切にしようと考えて行動する障害者がいる。これが障害者の力である。
これら背景を知っているという前提で個別性に基づく支援の在りようを考えることが、マナーではないだろうか。