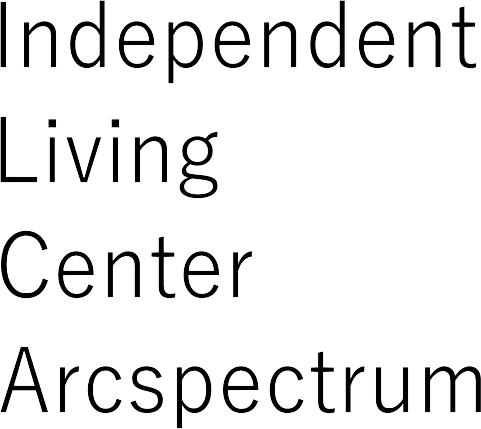ひゅうまん京都 寄稿文2015年11月
先月は休載させていただきましたが、とあるお仕事で、北は青森から南は沖縄までその県にある自立生活センターの訪問を行なっておりました。10月下旬の青森はすでに冬のよそおいで、いっぽう11月中旬の沖縄は夏でと、季節感覚が崩壊して自分の身体が壊れてしまわないか心配だった訳ですが、その時期の沖縄が夏だったことあってか元気になって帰ってきたという、いやはや人の身体はよく分からないものです。
さて、今回連載のお話しをいただいてからこの間「介助心得」についてお話ししてきた訳ですが、この号では「プライバシー」についてになります。介助心得の大きな柱の5つ目が「プライバシーを守ってください」ということになるのですが、私たちの介助派遣の提供はその人の自立支援(地域生活のノウハウを身につけること・精神的に自立すること等々)をともなってのもので、サービス種としては身体・家事支援ではなく、重度障害者が長時間利用できる重度訪問介護が占めています。
長時間の介助に入っていると、介助を利用する障害者の生活はよく見えてくるもので、身体の状態、食事の献立、~へ行った、~と会った、郵便物やFAXの内容など、生活すべての部面にわたってその障害者のプライバシーに向き合わざるを得なくなります。介助に入っている時間まるっと、その障害者のプライバシーに関わり、したがって介助者はその人の生活に入り込んでいると認識する瞬間かもしれません。もっとも、人によっては何がプライバシーにあたり何がプライバシーにあたらないのか分からないと聞くこともあり、その価値観に左右され、ましてや介助関係というのは人間関係で、人間関係を円滑にするためプライバシーを吐露することが気持ちの共有に必要だという理由で守られないということが多々あります。その場合、私は一人ひとりの介助者に対して「何がそうで何がそうではない」という判断がつかない場合それは全てがプライバシーであり、人のプライバシーを自分の価値観で規定してはいけない、ということを伝えています。
しかし、こうして介助者側が障害者のプライバシーを守っていたとしても、介助者のプライバシーが守られない場合があります。例えば、介助にきた介助者に対して「特定の介助者の愚痴を言う」「特定の介助者の私生活を言う」等々、それだけでなく介助を使う障害者同士や家族に対し「特定の介助者の愚痴を言う」「特定の介助者の私生活を言う」こともあり、また介助者に「他の障害者のことを聞く」ということもあるかも知れません。
こうしたプライバシーが守られていない状況というのは、障害者・介助者双方の生活を脅かすことになり、それは介助関係が顔色を見たり、ご機嫌を伺ったり、心根を装ったりすることにつながり、これは問題が起こった途端に人の好き嫌いで介助のキャンセルが常時起きたりする問題へと複雑化していくことでもあります。心理的虐待へと派生する重大な問題が含まれていると認識することが大切かもしれません。
それでは、私たちの自立支援をともなった介助派遣でもそうですが、介助者の勤務報告および報告・連絡・相談は障害者のプライバシーを破ることにつながるのではないか? 障害者からの介助者との関係性における悩み相談も介助者のプライバシーを破ることになるのではないか? という疑問も湧いてきます。まずはその前提は大切です。したがって、私は障害者および介助者たちにプライバシーに触れる機会になることはあるがけっして漏らさないルールは守ると伝えたうえで、その聞いた内容をどのように生かしていくのかを明らかにすることによって信頼関係のうえにそれを扱うことを考えてきました。相談役に抜擢された人は「問題解決の先頭に立つべき当事者は障害者と介助者である」という認識のもと、相談役は中立の立場で正しい情報を双方から得て問題を解決するための仲介者となる、これが私たちがプライバシーを扱う場合の明らかにしてきた例外です。原則と例外、例外のしかるべき理由を正しくとらえていきたいものです。