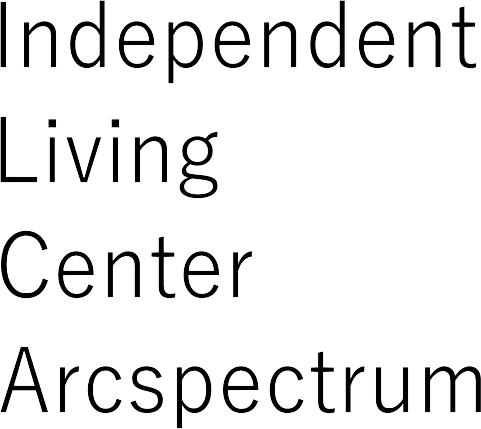ひゅうまん京都 寄稿文2006年4月
尊厳ある死、その向こう側。
3月25日付の新聞に大きく報道された事件がある。
ある医者が終末期医療の患者7人に対して人工呼吸器を取り外す処置を行った、というのである。死に向かいつつある状態の患者のむやみな延命をさける、これは消極的安楽死と言われるが、医療現場では積極的に支持される死でもある。どんなにがんばったとしても取れない身体的苦痛があり、治る病気にしか適切な処置は効果がない。
ここでの問題は患者がありのままに死を迎えたかどうかで、そのたびに、終末期医療患者に劇薬を投与した事件(東海大事件)などが引き合いにだされるであろう。そのためにはリビング・ウィルがありさえすれば良いと、いうことにもなるだろう。
折りしも、昨年には議員立法による尊厳死法案の上程が目指されていた。本人が事前に決めたなら、生きるための処置をしなくても良いのだ。例えば、末期のガン患者だけではない、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の人たちは−私も以前はこのような診断になっていたが−全身の筋肉が動かなくなり、息ができなくなるから人工呼吸器を装着して、握力がなくなるから眼球だけで意思の伝達をしながら生きているような、以前なら(今もそうだが)そこまでして生きなくてもいいじゃないかと言われていた人たちを対象に、どのように人としてありのままの死を迎えてもらうかが議論されていた。
自己決定ならそれは認められるのかもしれない。どうしようもない身体的苦痛などだれも耐えられはしない。もう植物状態で意識さえあるのかどうかも分からないのなら、本人の意志だとみなしうる人を相手に決めたらいいのかもしれない。まだある。末期ガン患者やALSの人はこうも考える。自分は動けなくなるし、何もできなくなる。その代わりに動くことになる人たちのことを思って、自己決定する。
しかし私はそうは思わない。そうとは、どれもこれも自己決定という天秤にかけられるものではないものばかりだということだ。身体的苦痛ならある程度までとれる医療がある、医療が必要だ。植物状態でもう死期に近いなら死ぬまで待てばよい。そして動けなくなる自分を思って、悲観して、嘆いて、死んでいく人には、それで答えていくしかないのだ。
誰にとっての尊厳か、がうやむやにされている。今年4月から施行された自立支援法にとって大切にされた尊厳は何かが、自己負担の発生した後に必ずやって来ると思う。人としての生活を送るのに必要な施策をとらずに、障害者の自己決定などを語れるとは思えない。おもえないのだが、それを語る人がこの世にはたくさんいる。やるべきことをやらずにいる人にとっての都合の良い尊厳であり、それが議論されているのは間違いないし、尊厳死法案でも自立支援法でも、人らしく生きれないことだけはわかる。