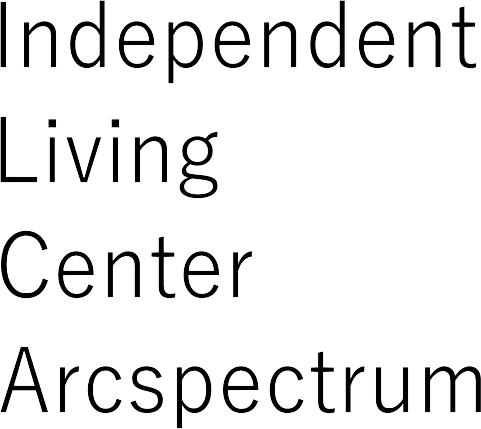ひゅうまん京都 寄稿文2006年5月
つながること、で、きづくこと
井上編集長から一本の電話がかかってきた。
用件の中身はこんなもの−4月から始まる自立支援法の定点観測を書いてみないか?−だったように記憶している。このお方とは、だいぶ以前にだけれども市長選に立候補されたときからの一方的な旧知の間柄で、私が胸を張って送りだした(投票した)人だった。現在の市長の顔が真っ青になるくらいの支持(投票)があったから、激動の京都が見えていたのは事実だった。ただ、それでもなお、一方的な旧知の間柄はここ数年保っていたはずだった。それがひょんなことにか、はたまたそうなる運命だったのか、「応益負担に反対する実行委員会」のメンバーとして顔をあわすことになり、一方的にこっちが知っていたということをしゃべることによって、旧知の仲は窮地を救う仲間(!?)として関係を築き始めたのだから不思議なこととしか言いようがない。
ひゅうまん京都をお読みの方には第一回目の連載記事が“ご挨拶”となってしまった訳で、ここであらためてごく短めの自己紹介をしようと思えば、いま関わっている当事者団体のこと、それが当事者の経験や体験をもとに成り立つということ、そんな団体の紹介をするのが良いと思ったので、思ったことをそのまま書くことにしよう。
私がいま関わっている団体は日本自立生活センター(JCIL)と言って、どんなに重い障害を持っていても、社会の支援を得ながらなら、自分が選んだ地域で暮らすことは可能だ、と思っている団体で、そう思っていることを実現させてきた当事者がいる。実現させてきた人がいるだけで、私もそれが実現できたのだ。在宅での暮らしは28年間にわたってのものだったが、その中では病院暮らしも長かった。親には本当に世話になった。私のものの見方や考え方の根底を培ってくれたのも親だったし、一人暮らしをしようと決意させたのも彼らの人生があったからだ。
ある日私に、知的障害を持つ女性の母親から電話がかかってきた。その母親は、自立支援法の申請書と世帯状況や資産などを書く申告書を隅から隅まで読み込み、もれなく必要な箇所は記載したのだが、後日ケースワーカに「ご家族の資産をこまかに記載されますと軽減策が受けられないので書かないで提出してもらって結構です」と言われたらしい。それをいかほどに判断したらよいだろうかという、必要なサービスが受けられなくなる事態をおもっての話だった。良心的なケースワーカーであることを説明し、娘さんのサービス申請に影響はないことも話すと、書き直しのために窓口へ行くと言われて電話は終わった。そんなことがあちこちで起こったのだろう。そうして4月を迎えたのだ、とも思う。
障害を持つ子どもの親が子どもを必死に守る。そのお母さんの人生と、これからの娘さんの人生と、いまの私の人生とで、それは必ず守れるはずだ。お母さん、きっと大丈夫です。僕たち重度障害者が娘さんのモデルになってこの社会で生きていますから。
いち息子から社会人へ、そして支援されるだけの側から支援もする側に立とうと決めたことによって、どちらの気持ちにも答えられる気がした。それはきっと、私の親が、私をどのように思って育てたのか、その意味を力強く感じた瞬間だったからなのではないか。