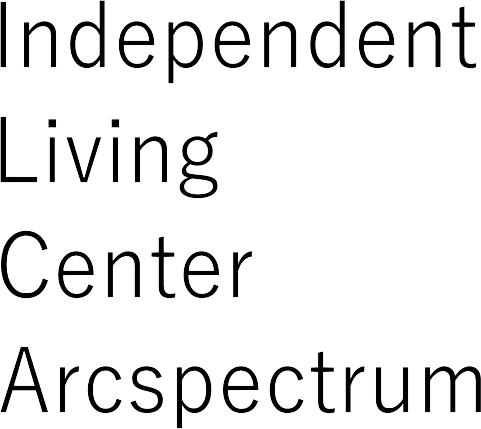ひゅうまん京都 寄稿文2006年7月
歴史から今を、いまから歴史を。
長い間続いた通常国会が終わった。
今国会の特徴だと思うのは「一定の国策にもとづく人間をつくる」という道筋が明確に見えたことであろう。国を愛する涵養を強制し(教育基本法の改定)、その心の名の下に海外で戦争をする国をつくり(改憲手続き法案)、反対だと思うだけで処罰され(共謀罪)、社会のお荷物はいまから排除(医療制度改革)というなんとも分かりやすい−逆に分かりやすすぎて怖い−が、そう意図された国づくりの実態がまざまざと見せつけられた国会であった。
いやはや、こんな国になればあっという間に私は捕まって刑務所に送還されるのだが、はたしてこんな立派な障害者を受け入れてくれるだろうか、という疑問が頭をよぎる。夜間は人工呼吸器でスーハースーハーとこよなく眠るし、不整な呼吸にはピーピーとアラームが対応してくれるし、タンの吸引はするしで、刑務所の安寧は訪れないだろう。看守さんは大変だろう。と同時に、障害を持って生きてきたこれまでのことで、例えば、障害者への義務教育や高等教育がこの社会に何を還元させているかというようなことに思い至ると、教育基本法の改定の動きにあたって障害者も充分に物申せるのではないかとも思うのだ。
養護学校の義務化がなされたのは普通学校の義務化よりも後の1979年である。それ以前は軽度障害者は入学できても、重度・重複障害者は就学猶予や就学免除という形で取り扱われていた。その当時、障害を「特性」だとみた人たちは義務化を望み、障害を「個性」だと見ていた人たちは義務化に反対した。このあたりの話しは茂木俊彦さんの著書(岩波新書)などが詳しく、よくご存知の方もいられると思うが、分かりやすく対比しただけなのでご容赦願いたい。私自身も障害は特性だと思うほうで、それは自立支援法を制定する際さかんに言われた個人的な利益にあたるものは私益だ、なんていう無茶苦茶な論理はおおかた障害は「個性」という安直な理解がその一端を担っているのではないかと踏んでいるのだが、極めてあぶないのだ。もっとも、義務化に反対した人たちの主張は義務化が障害児を地域の学校から排除するというもので、普通学校で障害児も学ぶ環境を作ろうというインクルージョンの発想が徐々に浸透しつつあるもとでは、その主張は間違いでもなかった。だからそんな教育環境にあった私たちが、いまの社会を担う主権者としてこの社会をどのように評価するか問われていることがあると思うのだ。
京都市で認定調査がはじまっている。調査員がケースワーカーである場合もあれば、民間の人であるということもある。聞き取り能力はまちまちだ。なぜまちまちなんだろうか。その人も人間だからだろうか。あるいは言語障害があるから聞き取りづらいのか。教育基本法改定の旗手を務める「教育改革国民会議」の座長は、「ある種の能力が備わっていない者が、いくらやってもねぇ。いずれは就学時に遺伝子検査を行い、それぞれの子どもの遺伝情報に見合った教育をしていく形になりますよ」とにべもなく述べている。露骨に優生思想を持ち出して教育を語る人間がこの世にいるのだが、先天的に良い遺伝というものが私には分からない。けれども、いずれにしても話ができない、話が聞けない人間はたいして教育に待たずとも良いではないか、ということがまかり通るのだろう。
こんな馬鹿な話しをさせておくことはない。人格の完成が教育の目的であるならば、その目的には「人の話を聞く力」と「人に話を伝える力」があるはずだ。学校教育の段階でそれが実現されることが望ましいし、実現されなかったにしても、いま向き合っている人との繋がりでそれを発揮しなければ教育の意味をゴミ箱に放り投げてしまうことになるじゃないだろうか。