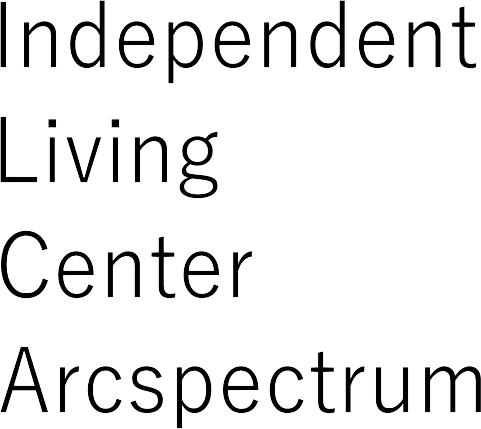ひゅうまん京都 寄稿文2008年5月
最初の聴衆であること
その人の慟哭が音楽になっているのだ。子どもの日の夕暮れどき、とある一室で催された総会での一幕に「佐村河内守―人と作品」を井上吉郎さんが語った。佐村河内さんを、私なりに、尾ひれをつけて語るのだが、その前に一年ぶりの再会であった井上さんについて話そう。
大阪の病室で、どんな話が交わされたかは覚えていない。しかし、私がひとしきり現状を語った後、今後の人生について再び弁護士を目指すもよし、何をするのもよしという、そんな彼を見て、井上さんは相も変わらず井上さんだと、感じた。若人への送る言葉は、自身に何が起きようとも心得ている人だ。総会のとき、自ら進行をしながら、機転の利く笑いをもって井上吉郎ここにあり、と認識させたのもたしかだった。けれども私が感じたのはそれでではなく、一人ひとりの歓談が行われているときに、不躾で、自分本位な質問をかけまいと、和に注意を払う姿で、私は、井上吉郎がここにいると思ったのだった。この連載の「和して同ぜず」は井上さん自身である。その言葉をもらって書いている。
さて、そんな井上さんに狂言の楽しみを教えてもらったが、佐村河内さんについても教えてもらった。ここからは佐村河内さんの話だが、現代にいきるベートーヴェンと称される知る人ぞ知る作曲家だそうだ。かの楽聖と同じく聴覚障害をもち、片頭痛に悩まされながら精神障害とも向き合う。これだけの話で、孤高の作曲家という、イメージを持つ。映画「バイオハザード」やプレイステーション2用ソフト「鬼武者」全編にわたって作曲をしたということで、遠からず近からずといった感があるが、知らなかった。
彼の音楽について話を進めてみる。慟哭―何かを伝えるという気概に満ち溢れた音が紡ぎだされていて、その音を聞けば、音が言葉の杖であることに気づくだろう。無調、絶対的な西洋音楽の調性を排して、自らの感性により近い音が作られていく手法は、彼を知る一断片でしか過ぎないが、そういった手法で作曲した人に武満徹もいる。私は彼の曲を聴く。「言葉の杖」というのは武満徹の言葉であり、音楽家に大事なのは、聴くということであり、それはこの社会の出来事、自然、それらの最初の聴衆であることだといった。だから音楽を聴けばその人となりを知るには十分なのだが、私たちには難解なことが多い。だから武満徹は多くの著作を残してそれを言葉の杖とした。幸いなことに、佐村河内さんにも著作があるので、言葉の杖を聴き、言葉の杖を読むことをなさってもよろしいと思う。
生きることが大変だ。生きている証を表現し、発表するにも大変だ。そんなことを思うかも知れない。そうだと思うけれど、でも私は、それでも楽聖を思うとき、武満徹を思うとき、自分の障害と向き合うときに、彼の今後の活躍に明るさを見い出すことしかできないのである。